
自由学校を作ろう
難しい話になりますが
最近はいわゆるお勉強ができる子どもを育てるというより
コミュニケーション能力の高い子どもを育てることが
大切であると様々な世界の方が言われています
実際いろいろな人と働く機会を通して
学力よりも人と協力できる力や忍耐力
失敗してもあきらめない精神力などが必要だなと
つくづく思います
そしてそれは体験により培われることが実証されています
学校も今変わろうとしています
保育所や幼稚園との連携を重視し
1年生に入った時のギャップを解消しようとする試み
異年齢授業による教えあい支えあい
自主性を育てる取り組み
一挙にいろいろ始まって
先生たちも変化に追いついていくのに大変だと思います
保育所の運営を始めて16年目になります
その間子どもたちの変化にたくさんのことを学ばせてもらいました
一番は大人中心ではだめだということです
子どもを取り巻く環境が劇的に変わっているのに
これまでの経験で様々な課題を乗り切ろうとしても
とても無理だということは子どもたちから教えてもらいました
だから子ども中心になろう
子どもの姿から学ぼう
取り組みを始めて8年になりますが
やっと少しずつ成果が出てきました
そして学校に進学していきます
でも今の学校にすんなりなじめる子はいいのですが
そうではない子が増えてきています
それは学校でも感じられていることです
どうすればいいのだろうと考えてきました
そして行き着いたのが
子どもたちが楽しいと思う学校を作ろうということです
もちろん文科省認定の学校です
子どもたちに選択肢を作ろうということです
これまでとは違う教育の在り方にアプローチしようということです
大人があまり手を出さず子どもたちに任せよう
子どもは大人が考えているよりはるかに高い能力があります
自分たちで何を学ぶのかを決めさせよう
自分たちで決めれば
させられるのとは違って積極的になります
保育所の子どもたちを見ていて確信します
そう考えていたところに
それを実践している学校を発見しました
和歌山県にある「きのくに子どもの村学園」です
もう30年前から子ども中心の学校をやっておられます
全国に5か所の学校を運営されています
行って見てきました
基本的に危険なこと以外は
やってはだめということがないので
子どもたちは自分たちで話し合いを進め
自分たちで決め行動し
そして振り返りをしていました
小さな家一軒がほとんど子どもたちだけで作られているのは
びっくりしました
できるんですねぇ
それで分校を作ってもらおうとお話に伺ったのですが
もう分校は作らないとのこと
だったら自分たちで作るしかないかと
有志とともに今作る準備をしています
できるの?だいじょうぶ?という
素朴な疑問をたくさんいただいております
そんなこと断言できません
しかしやってみないとできるかどうかわからない
というのは断言できます
私たちも子どもたちと同じです
まずやってみる
成功するまでやってみる
大人も頑張ってるぞという姿を
子ども達に見てもらいたいと思います
そこでどんな学校になるのかというお手本の話を
きのくに子どもの村理事長の堀 信一郎先生に来ていただいて
お話を聞く会を設けます
7月30日(土)14:00~16:00
庄原市ふれあいセンター
参加費は1000円必要です
ぜひワクワクする話をお聞きください

どんより曇っているのに
小さなプールで
芋の子状態

水の流れ
飽きないのですね
ずっとやってます

最近
木登りにはまってます
上まで行けるようになったんよね

家族みたいですね
お話を聞いてもらって
ちょっと満足

一人がやり始めると
競争になります
一つ飛ばしが目標みたいです

木陰の
ちょっと高いところ
大きくなった気が
するんですかね

オッ オケラ
大きいね
見せてくれるん?

何かくれてるの?
見えてるよ
見つかったね
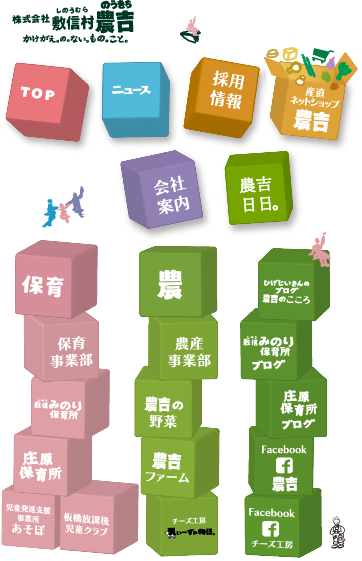





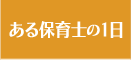
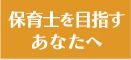
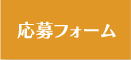


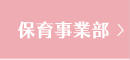
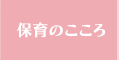
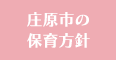
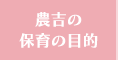
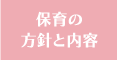
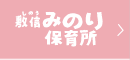
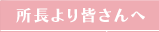
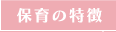
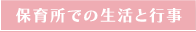
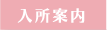

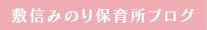
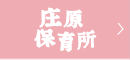
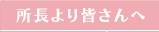
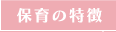
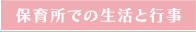
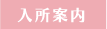
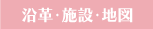
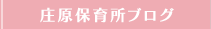
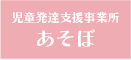
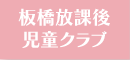


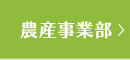

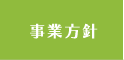
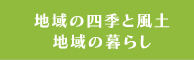
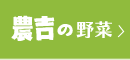






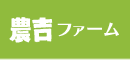
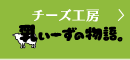
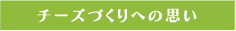
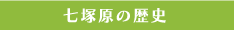









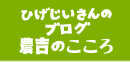
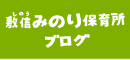
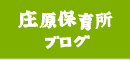




 ©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.
©株式会社敷信村農吉 2019 All Rights Reserved.